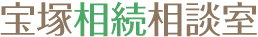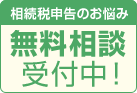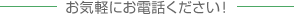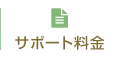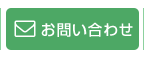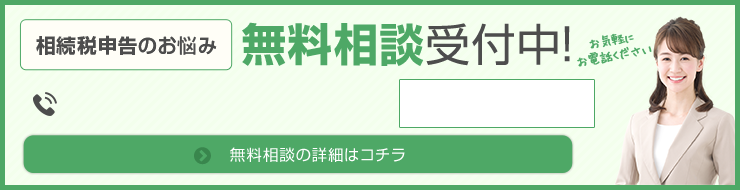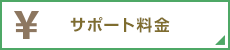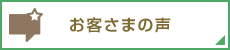【税理士監修】相続税の税務調査で指摘される「名義預金」とは?判断基準と具体的な対策を徹底解説!
「子や孫の将来のために、少しずつ貯金してあげたい」
「高齢になった親の代わりに、預金を管理している」
家族を想う気持ちから始めたこれらの行為が、意図せず「名義預金」と判断され、将来多額の相続税を課される引き金になる可能性があることをご存知でしょうか。
相続税の税務調査で最も指摘されやすい項目のひとつが、この「名義預金」です。良かれと思って管理していた預金が、ある日突然、税務署から「故人の隠し財産」とみなされてしまうかもしれません。
この記事では、税理士監修のもと、相続税における名義預金の判断基準から、税務調査で指摘されないための具体的な生前対策、そして万が一に備えた相続発生後の対処法まで、網羅的に解説します。大切な家族と資産を守るために、正しい知識を身につけましょう。
「うちも名義預金かも?」親や子、孫名義の口座に潜む相続税のリスク
「子や孫の名前で口座を作って、自分がお金を入金・管理している」「生活費を管理しやすいように、専業主婦の妻の口座に夫の給料を入れている」といったケースは、多くのご家庭で見られます。
しかし、これらの預金は、口座の名義人が誰であれ、実質的な所有者が亡くなった方(被相続人)であると税務署に判断された場合、その方の相続財産として相続税の課税対象となります。
もし申告から漏れていれば、本来納めるべき税金に加えて、ペナルティとして重い「追徴課税」が課される可能性があります。家族間の愛情表現や便宜上の管理が、思わぬトラブルに発展しないよう、まずは名義預金のリスクを正しく理解することが重要です。
そもそも「名義預金」とは?税務署が認定する4つの判断基準
名義預金とは、簡単に言えば「口座の名義人と、そのお金を実質的に所有・管理している人が異なる預金」のことです。例えば、口座の名義は「子」でも、そのお金を入金し、通帳や印鑑を管理しているのが「親」である場合などが典型例です。
税務署は、ある預金が名義預金に該当するかどうかを、形式的な名義だけで判断するわけではありません。以下の4つの基準を総合的に見て、実質的な所有者は誰なのかを判断します。
- 預金の原資は誰が出したか
その口座に入っているお金は、誰の収入や資産から拠出されたものでしょうか。例えば、お子さんやお孫さん自身に十分な収入がないにもかかわらず、口座に多額の預金があれば、その原資は親や祖父母であると推測されます。 - 通帳や印鑑は誰が管理していたか
口座の通帳、キャッシュカード、届出印を名義人本人ではなく、親や祖父母が管理・保管しているケースは、名義預金と判断される非常に強い要素となります。 - 名義人はその預金の存在を知っていたか
「孫が生まれたお祝いに」と、お孫さん本人に知らせずに口座を開設し、入金を続けているケースがあります。このように、名義人本人が口座の存在すら知らない場合、その預金は本人の意思で管理・使用できるものではないため、名義預金と認定されます。 - 名義人はその預金を自由に使うことができたか
名義人が口座の存在を知っており、通帳等を持っていたとしても、お金を使う際に「親の許可が必要だった」「使途を報告する義務があった」など、自由な使用が制限されていた場合は、実質的な所有者は親であると判断される可能性があります。
なぜバレる?名義預金が税務調査で見つかる理由とペナルティ
税務署は「国税総合管理システム(KSK)」という強力なシステムを用いて、全国民の納税状況や資産情報を一元管理しています。
死亡届が提出されると、その情報は税務署にも連携され、相続税の調査が必要と判断されれば、被相続人だけでなく、その家族名義の口座についても過去の取引履歴が確認されます。
名義預金が見つかった場合には、以下のような追徴課税が課されます。
- 過少申告加算税(税率10〜15%)
- 無申告加算税(税率15〜20%)
- 重加算税(税率35〜40%、悪質な場合)
- 延滞税(日数に応じて加算)
【生前の対策が鍵】名義預金と指摘されないための具体的な方法
- 贈与契約書を作成する
誰が誰に、いつ、いくら贈与したか明記し、署名・捺印された契約書を作成しましょう。 - 銀行振込でお金を渡す
現金の手渡しは避け、必ず振込で証拠を残します。通帳記録は有効な証拠になります。 - 名義人自身が口座を管理する
通帳・印鑑は受贈者が管理し、自由に預金を使える状態にしておくことが大切です。
これらの対策は、暦年贈与を行う際にも非常に重要です。
【相続発生後】すでに名義預金がある場合の対処法
- 相続財産として正直に申告する
名義預金も被相続人の財産として含め、正しく申告します。 - 遺産分割協議で合意する
名義預金を含めた財産の分け方を、相続人全員で話し合い決定します。 - 税理士に相談する
判断に迷う場合や不安がある場合は、相続専門の税理士に相談するのが安心です。
相続税の名義預金に関するQ&A
Q1. いくらまでなら名義預金とみなされませんか?
A. 金額の基準はなく、実質的な所有者が誰かを4つの判断基準で総合的に判断されます。
Q2. 名義預金に時効はありますか?
A. 相続税には原則5年(悪質な場合は7年)の時効がありますが、名義預金には贈与の時効は基本的に適用されません。
Q3. 専業主婦や学生名義の預金も対象ですか?
A. はい。本人に収入がない場合、その原資が誰かが重要です。
Q4. 贈与税を払っていれば名義預金ではないですか?
A. 贈与税の申告は有力な証拠ですが、それだけで万全ではありません。管理状況も重要です。
まとめ:将来のトラブルを避けるために、今すぐ口座の確認を
名義預金は、家族への善意から始まることが多いですが、税務上はトラブルの火種になり得ます。
今のうちに口座の状況を家族で確認し、必要に応じて税理士に相談することが、将来の安心に繋がります。
1.初回相談は無料です!(要予約)
当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-829-740になります。
お気軽にご相談ください。
2. 無料相談の実施
ヒアリングシートを基にご相談者様からお話をお伺いいたします。
ご相談内容を明確にし、必要な相続手続きを明確にします。
また、相続の基本ルールのご説明や、必要事項の聴取を行います。
その後、次回面談日を決めます。
3.お申込み/相続手続きの開始
ご相談後、ご納得いただければ、お申し込みをしていただきます。
当事務所が、お客様の相続手続き完了までの一切の不安にお答えします。
また、弁護士・司法書士等の各専門家との受け渡しも極力少なくて済むように工夫をしております。
※その他、不動産・遺品の売却アドバイスなど相続手続き完了までのあらゆるご相談に対応します。
※個別に依頼すると高額になりがちな専門手続きを一括でコーディネートして、必要な手続きをだけをオーダーメイドいたします。
4.相続手続き完了報告

全ての相続手続きが完了しましたら、そのご報告と完了書類一式をお渡しいたします。
5.アフターフォロー
お客様の今後の相続に関する不安にお答えいたします。
また、ご希望に沿った相続対策についてもご提案をいたします。
- 神戸三田エリア及び近隣地域で相続税などに関するご相談は当事務所にお任せください
- 税理士法人矢野会計 代表 矢野浩一郎より神戸三田エリア及び近隣地域にお住まいの皆様へ
- 神戸三田、近隣エリアに所在する不動産を相続する方へ
- 神戸三田相続相談室へのアクセス
- 神戸三田相続相談室の紹介
- 相続のプロが教える!三田市で後悔しない相談先の選び方と注意点
- 相続税申告の期限とは?申告までの流れや延長できる場合を解説!
- 【税理士監修】相続税の税務調査で指摘される「名義預金」とは?判断基準と具体的な対策を徹底解説!
- 三田市のみなさまへ
- 三田市で相続税に強い税理士の選び方|申告は必要?基礎控除から無料相談まで解説
- 相続税申告は神戸三田相続相談室にお任せください!